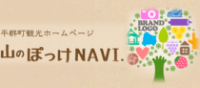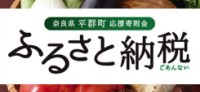本文
ひとり親家庭等医療費助成制度
印刷ページ表示
記事ID:0001283
更新日:2024年12月2日更新
平群町に在住(住民票がある)の、ひとり親家庭の親および子どもが、病気やけがで健康保険が適用になる診療を受けた場合の医療費(自己負担分)を助成する制度です。
対象者(注:所得要件あり)
次のすべてを満たす方が対象となります。
- 平群町に住所を有する、
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童とその子を監護している父・母
- 父母のいない18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童と、その子を養育している配偶者のいない方または婚姻したことのない方
- 国民健康保険・社会保険等の健康保険に加入している方(無保険の方や生活保護受給者は除く)
- 平群町の他の福祉医療制度を受けていない方
- 本人および扶養義務者の所得が児童扶養手当施行令に規定する額未満である方
(扶養義務者については下記「扶養義務者とは」をご確認ください。)
所得制限(児童扶養手当施行令に規定する所得要件)
児童扶養手当法施行令に規定する額については、下記「児童扶養手当法施行令に規定する所得要件」のページをご確認ください。
- 所得が未申告の方は、助成を受けることが出来ません。
- 収入の有無にかかわらず税務課へ申告をおこなってください。
- 養育費や非課税年金(遺族年金・障害年金等)の受給状況も健康保険課で申告していただきます。
助成範囲
健康保険が適用となる診療を受けた場合の医療費(自己負担分)を全額助成します。(入院時の食事にかかる標準負担額等を除く)
予防接種や健康診断、文書料等の保険外診療は助成対象外です。また、助成にあたっては健康保険から給付された高額療養費や家族療養附加金等は除外します。
学校管理下でのケガで、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付対象となるものについては、助成対象外となります。
助成方法
奈良県内の医療機関等で受診した場合
- 18歳に達する日以後の3月31日までの間にある児童(現物給付方式:支払不要です)
医療機関等窓口で、マイナ保険証または資格確認書等と「医療費受給資格証」を必ず提示してください。医療費(保険適用の自己負担分)は現物給付となり、支払い不要です。 - 児童以外(自動償還方式:申請不要です)
医療機関等窓口で、マイナ保険証または資格確認書等と「医療費受給資格証」を必ず提示し、医療費を支払ってください。支払った医療費のうち保険診療分を届出いただいている登録口座に自動的に振込みます。(医療機関からの報告により、原則診療月の2ヶ月後、25日に振込みます。)
(注)土日祝日の場合はその翌日になります
奈良県外の医療機関等で受診した場合、及び県内の医療機関で「医療費受給資格証」の提示ができなかった場合(注)申請が必要です。
- 県外医療機関では「医療費受給資格証」は使用できません(児童の場合、現物給付方式の対象となりません)。健康保険課窓口まで医療費助成金支給申請書と領収書原本(保険診療点数記載のあるもの)を提出してください。
- 領収書は原本を提出していただきます。領収書が無い場合や、原本を提出できない場合は申請書様式の裏面に医療機関等で証明を受けてください。
- 申請はひと月分をまとめて、受診月の翌月以降に行ってください。20日までの受付分を、翌月に振込みます(時効は、医療保険の自己負担額を医療機関等に支払った日の翌日から5年です)。
- 医療費助成金支給申請書 [PDFファイル/142KB]
- 医療費助成金支給申請書 記載例 [PDFファイル/194KB]
資格の新規認定について
出生・転入・離婚や死別時等で新規に資格を取得される場合は次のものが必要です。
(注)資格認定は申請日からです。お早めにお手続きください。
- 対象者全員の加入医療保険情報がわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ等)
- 助成金振込み希望口座の通帳、キャッシュカード
- マイナンバーがわかるもの(対象者全員分および扶養義務者全員分)
マイナンバー確認の詳細は、次のPDFファイルをご確認ください。
「個人番号(マイナンバー)を利用する事務」に関する手続きについて[PDFファイル/404KB] - 申請事由を証明する書類(戸籍謄本、児童扶養手当証書等)
- 本人および扶養義務者の所得証明書(扶養人数・控除額等記載分)が必要な場合があります。詳しくはお問合せください。
(注)平群町で所得が確認できる方は所得証明書の添付は不要です。平群町にお住いで所得が未申告の方は、収入の有無にかかわらず申告が必要になります。 - 遺族年金を受給している方は、直近の振込額決定通知書や年金証書など
受給資格証のご使用にあたって
- 届出いただいた内容(住所・氏名・扶養義務者・所得状況・加入医療保険・届出口座等)に変更が生じた場合は、助成金を支給できなくなる場合がありますのでお早目に変更手続きをおこなってください。
- 医療機関窓口での支払いについて、貸付制度を利用できる場合があります。受診される前に貸付資格の認定が必要です。あらかじめ健康保険課へご相談ください。
- 医療費助成を受けた医療費については、確定申告の医療費控除の対象となりません。