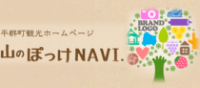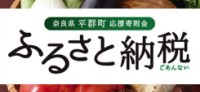本文
国民健康保険で受けられる給付
| こんなとき | 必要なもの | 給付 | |
|---|---|---|---|
| 一般的なもの | 病気になったとき、 けがをしたとき、 歯の治療など |
マイナ保険証または資格確認書等(医療機関の窓口で提示) | 治療費の7割(または8割)が保険から支払われます。 |
| 特殊なもの | 旅行中の急病などやむを得ない理由で、マイナ保険証または資格確認書等を提示できなかったとき | 診療報酬明細書(レセプト)、領収書、マイナ保険証または資格確認書等、振込先のわかるもの | 書類を添えて、申請書とともに窓口へ提出してください。 審査をして保険診療分の7割(または8割)が払い戻されます。 (医療機関への支払い後2年を経過しますと、時効により請求できなくなります) |
| コルセットなどの補装具をつくったとき | 医師の意見書、領収書、マイナ保険証または資格確認書等、振込先のわかるもの (注)靴型装具に係る申請には、当該装具の写真(患者が実際に装着する現物であることが確認できるもの)が必要です。 |
||
| 治療上、マッサージ、はり、灸などを必要としたとき | 医師の意見書、領収書、マイナ保険証または資格確認書等、振込先のわかるもの | ||
| 移送費 (入院・転院など) |
医師の意見書、移送に使用した経路のわかるもの、領収書、マイナ保険証または資格確認書等、振込先のわかるもの | ||
| 海外渡航中に病気やけがで治療を受けたとき(治療目的で渡航した場合は対象となりません) | 診療内容明細書・領収明細書(この2つには日本語の翻訳文が必要です。)、マイナ保険証または資格確認書等、パスポート、振込先のわかるもの (注)渡航前に必ず健康保険課へお問い合わせください。 |
||
| 高額療養費 |
領収書、マイナ保険証または資格確認書等、振込先のわかるもの |
詳しくは次のリンクをご確認ください。 70歳未満のかたの高額療養費 [PDFファイル/56KB] 70歳以上75歳未満のかたの高額療養費 |
|
| 出産育児一時金 | 領収書、マイナ保険証または資格確認書等、母子健康手帳、振込先のわかるもの |
488,000円(時効2年) ※令和5年3月31日以前の出産の場合はお問い合わせ下さい。 |
|
| 葬祭費 | マイナ保険証または資格確認書等、葬祭費用に係る領収書、振込先のわかるもの | 30,000円(時効2年) | |
70歳未満のかたの高額療養費
同じ人が、同じ月内に同じ医療機関に支払った自己負担額が、次の表の限度額を超えた場合、申請によりその超えた分があとから支給されます。
世帯構成が変わらずに奈良県内の市町村間で住所を異動した月は、異動前と異動後の限度額がそれぞれ2分の1となります。
| 所得区分 (注2) | 3回目まで | 4回目以降 (注1) | |
|---|---|---|---|
| ア | 901万円超 | 252,600円 +医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1% |
140,100円 |
| イ | 600万円超 901万円以下 | 167,400円 +医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1% |
93,000円 |
| ウ | 210万円超 600万円以下 | 80,100円 +医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1% |
44,400円 |
| エ | 210万円以下 (住民税非課税世帯を除く) |
57,600円 | 44,400円 |
| オ | 住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
(注1)過去12カ月で、同一世帯での支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
(注2)基礎控除後の「総所得金額等」に当たります。
限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証について
高額な診療を受けたとき、資格確認書等と一緒に限度額適用認定証等を提示することで、同じ月内の医療機関等の窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
なお、マイナ保険証をお持ちのかたは、マイナ保険証をお使いいただくことで限度額の適用を受けることが出来るため、限度額適用認定証等の発行はありません。
高齢者(70歳から74歳のかた)の医療
国民健康保険加入者で70歳から74歳のかたは、所得に応じて医療機関等で支払う自己負担割合が2割負担と3割負担に分かれています。
マイナ保険証または資格確認書等をお使いいただき、医療機関等を受診して下さい。
お医者さんにかかるときの自己負担割合
お医者さんにかかるときの自己負担割合は、所得区分によって異なります。所得の申告は忘れずにしましょう。
- 2割負担になる人の所得区分
一般 現役並み所得者、低所得者1・2以外の人 低所得者2 同じ世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税世帯の人(低所得者1以外の人)。 低所得者1 同じ世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万6,700円として計算)を差し引いたときに0円となる人。 - 3割負担になる人の所得区分
現役並み所得者
同じ世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳から74歳までの国保被保険者がいる人。
ただし、住民税課税所得が145万円以上でも、下記(1)(2)(3)いずれかの場合は、「一般」の区分となります。同じ世帯の70歳から74歳までの国保被保険者数 収入 (1) 1人 383万円未満 (2) 同一世帯で国保被保険者から後期高齢者医療制度に移行した人を含めて、合計520万円未満 (3) 2人以上 合計520万円未満
※同一世帯の70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者の「基礎控除後の総所得金額等」の合計額が210万円以下の場合は「一般」の区分となります(申請の必要はありません)。
70歳以上のかたの高額療養費
70歳以上の人が、同じ月内に医療機関で支払った自己負担額が、次の表の限度額を超えた場合、申請によりその超えた分があとから支給されます。
世帯構成が変わらずに奈良県内の市町村間で住所を異動した月は、異動前と異動後の限度額がそれぞれ2分の1となります。
70歳以上75歳未満のかたの限度額について [PDFファイル/479KB]
70歳以上のかたの限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証について
高額な診療を受けたとき、外来・入院とも限度額は上記の表のとおりですが、「低所得者2・1」のかたは「限度額適用・標準負担額減額認定証」、「現役並み所得者2・1」のかたは「限度額適用認定証」が必要となりますので、事前に健康保険課に交付の申請をしてください。ただし、「現役並み所得者3」と「一般」のかたは、限度額認定証がなくても限度額適用を受けることが出来るため、限度額認定証の発行はありません。
また、マイナ保険証をお持ちのかたは、マイナ保険証をお使いいただくことで限度額の適用を受けることが出来るため、限度額認定証の発行はありません。