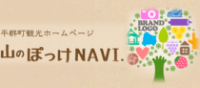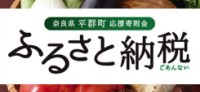本文
後期高齢者医療保険料のお知らせ
保険料
7月中旬に保険料額決定通知書が送付されます。(被保険者一人ひとりが納めます。)
年間の保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、前年の所得に応じて負担する「所得割額」の合計です。(保険料率は、奈良県内統一のものです。)
| 均等割額 |
被保険者1人当たり 51,500円 |
= |
被保険者の保険料 (100円未満切り捨て) ただし上限額は80万円 |
|---|---|---|---|
| + | |||
| 所得割額 |
(総所得金額等-基礎控除43万円) ×所得割率10.55% |
||
■所得が低い方は、保険料の「均等割額」が世帯の所得によって次のとおり軽減されます。
| 軽減割合 | 同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額 |
|---|---|
| 7割軽減 | 基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等※の数-1)以下の世帯 |
| 5割軽減 | 基礎控除額(43万円)+30.5万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等※の数-1)以下の世帯 |
| 2割軽減 | 基礎控除額(43万円)+56万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等※の数-1)以下の世帯 |
※一定の給与所得者(給与収入55万円超)または公的年金等に係る所得がある方(公的年金等の収入金額が、65歳以上で110万円超または65歳未満で60万円超)
※軽減判定は4月1日(4月2日以降に加入した方は加入日)の世帯状況でおこないます。
■社会保険等の被扶養者であった方については、資格取得後2年間に限り、均等割額が5割軽減されます。(所得割額は課されません)
(注意)
- 基礎控除額等は、税制改正などで今後変わることがあります。
- 所得が少ない世帯に属する被保険者は、均等割額が軽減されます。
- 軽減措置を受けるには、税法上の申告義務のない方(障害年金、遺族年金等受給者や被扶養者および所得のない方)であっても、所得が無い(0円であること)申告を行う必要があります。
保険料の納付方法
特別徴収納付時期
| 仮徴収 | 本徴収 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 (1期) |
6月 (2期) |
8月 (3期) |
10月 (4期) |
12月 (5期) |
2月 (6期) |
「特別徴収」
受給されている年金から保険料が天引きになります。4月に仮徴収額決定通知書が送付されます。
(注)介護保険料が天引きされている年金額が年額18万以上の方は、年金から保険料が天引きされます。ただし、介護保険料と合わせた保険料額が、その年金額の2分の1を超える場合は、普通徴収になります。
普通徴収納付時期
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 |
「普通徴収」
- 納付書で保険料を金融機関で納めます。(特別徴収の対象とならない方)
- 口座振替の方は各期納付期限の日に届出口座から振替納付します。