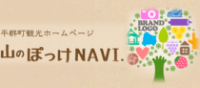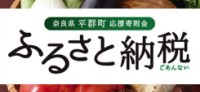本文
県指定 ツボリ山古墳
印刷ページ表示
記事ID:0001084
更新日:2021年1月25日更新
| 区分 | 県指定/史跡 |
|---|---|
| 員数 | 1基 |
| 所在 | 平群町福貴1049-108.109 |
| 所有 | 平群町 |
| 指定 | 昭和48年 3月15日 |
| 時代 | 飛鳥時代 |
| その他 |
生駒山地より東に延びる丘陵の南斜面に築造された古墳で、墳丘は造成工事で削平され、当初の姿を留めていないが、一辺20m程の方墳の可能性が考えられている。
主体部は南に開口する横穴式石室で、玄室長4.25m、幅2.2~2.55m、高さ2.45m。羨道は長さ4.65m、幅1.7~1.82m、高さ約1.7m。玄室は二段積みで、2石目が大きく内傾し、前壁も同様だったとみられる。
玄室中央と羨道に各一基の二上山白色凝灰岩製の刳抜式(くりぬきしき)家形石棺が納められている。玄室棺は蓋が半分のこり、わずかに下方に傾いた縄(なわ)掛(かけ)突起の形態が確認できる。玄室棺は身の長さ2.45m、幅1.17m、高さ0.8mあり、長さ1.55m、幅0.55m、深さ0.42mのくり込みがある。蓋は、幅1.19m、高さ0.7m。小口部に各1個、側面に各2個の縄掛突起がやや下向きに造り付けられ、内部には深さ0.11mのくり込みがある。羨道棺はやや小振りで、長さ2.35m、幅1.19m、高さは不明。
古くに開口し、石室の整備に伴う発掘調査では当初の副葬品は出土せず、石室構造、石棺形態より7世紀初頭の築造と考えられている。