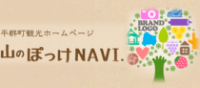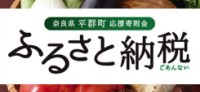本文
県指定 銅造(どうぞう)毘沙門天(びしゃもんてん)立像(りゅうぞう)
印刷ページ表示
記事ID:0001064
更新日:2021年1月25日更新
| 区分 | 県指定/彫刻 |
|---|---|
| 員数 | 一 躯 |
| 所有 | 平群町信貴山2280番地 信貴山朝護孫子寺 |
| 指定 | 平成12年 3月31日 |
| 時代 | 平安時代 後期 |
| その他 | 霊宝館で展示 |
県下では数少ない兜跋(とばつ)毘沙門天像で、寺伝で山崎長者の念持仏とする。霊宝館に安置され、小さな厨子に収められる。鋳銅製で鍍金の痕跡が残り、高さ17.2?の小像ながら精緻な造りの毘沙門天立像である。高い宝冠をかぶり、海老籠手(えびこて)を付け、長い外套状の鎧を着た西域風の姿で、足下に地天女はないものの、四天王のうちの一体としてではなく、単独の兜跋毘沙門天像と考えられている。
左手を屈臂(くっぴ)して塔(亡失)を捧げ、右手は挙げて戟(ほこ)(後補)を執る。腰を左に捻り、脛当(すねあて)をつけ沓(くつ)を履き、両足を開いて立つ。鎧には、鳳凰・宝相(ほうそう)華(げ)・小札(こざね)模様が細かく毛彫りされた優品である。胸甲や獅噛(しかみ)をつけない鎧の形式は、唐代の請來品として著名な東寺像(国宝)より、西域風をよくとどめている。 兜跋像の鋳銅仏は珍しく、信貴山の高僧の念持仏であろうと推測されている。