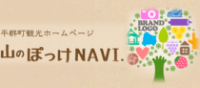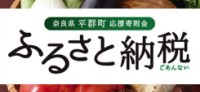本文
重文 藤田家(ふじたけ)住宅
| 区分 | 重文/建築 |
|---|---|
| 員数 | 一棟 |
| 所有 | 平群町福貴1523番地 藤 田 文 雄 |
| 指定 | 昭和53年 1月21日 |
| 時代 | 江戸時代 中期 |
| その他 |
藤田家住宅は北福貴の高台にあり、南には灰田川の谷を見下ろす要地にある。整った大和棟(やまとむね)の民家として指定され、昭和59、60年度に半解体修理が行われた。 修理の際の調査により、当初は元禄年間(1688~1703)に建てられた萱葺(かやぶき)の入母屋造りで、三度の改修が確認された。第一次改造は18世紀後半、第二次改造は文化4年(1807)、第三次改造は明治末年(1912)に実施されている。修理後は、指定の趣旨から大和棟の形態が整った第一次改造の姿に復元されている。茅葺き入母屋造り構造の前身建物の古図が伝わる。
母屋は、桁行(けたゆき)18.8m、梁間(はりま)11.8mの規模があり、段違いの棟で、主屋の本屋根は切妻造茅葺、両妻は高塀造本瓦葺。庇も瓦葺で、落屋根は中央部に煙出しのある切妻造本瓦葺。本屋根の下は居間や座敷などの居住空間、落屋根の下は勘定部屋(馬屋)、土間、釜屋などの作業空間となっている。
外見の特徴として土間につながる内玄関以外に、代官などの賓客用として直接みせのまに続く外玄関がしつらえられている。指定外であるが、右手奥に貴賓室である上段の間が別座敷(指定外)となっていた。内部では、組物は巨材が用いられ、釜屋の梁にはなぐり刃が入り、上手の梁はウリムキに仕上げられ、天井は松の根太組である。部屋の天井は全て竹が用いられた簀子(すのこ)天井で、座敷だけは竹を押しつぶしたひしゃぎ竹、他は割竹による簀子天井となっている。「みせのま」と「なかのま」間は竹製の欄間、敷居の一部は突き止め溝となっており、古式を残している。
藤田家は、系図によると武蔵国榛沢郡藤田庄(埼玉県本庄市藤田)に藤原氏の荘園があり、その荘官出身。鎌倉期に武士化して上杉氏に仕え、藤田姓を名乗る。その滅亡後は甲斐武田氏に仕え、室町期に武田氏が滅ぶと大和に移り、山辺郡を本拠に筒井氏・藤堂氏に仕えた。元和(げんな)(1615~1624)の頃に平群に転封され、帰農して庄屋を歴任した。